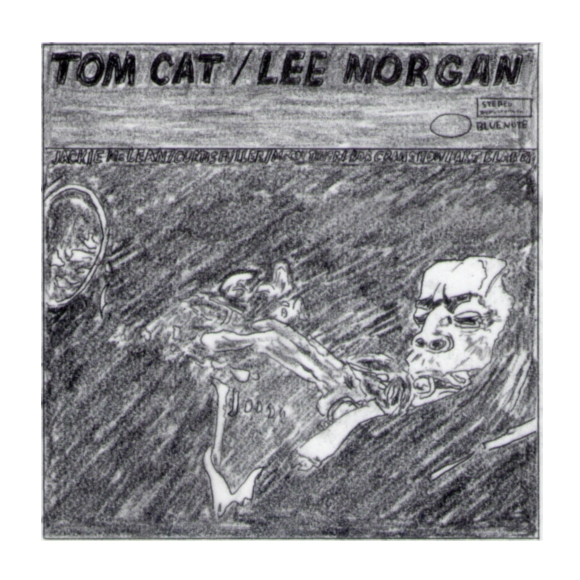 ←click!!
←click!!
出来らあっ! …ということで、今日は 『スーパーくいしん坊』 について考えてみたいと思います。 前回 、後半の最初のところで、この台詞を使わせて貰ったんっすが、元ネタは何なのかと思ったら、 これ 。 なるほど、これは酷いっすな。 原作は牛次郎、漫画はビッグ碇という 『包丁人味平』 を生み出したコンビによる作品である。 ほぉ。 それを聞いて俄然、興味が湧いてきました。 不朽の名作っすよね、味平。 僕が少年だった頃から通っている床屋には 「週刊少年ジャンプ」 が置いてあったんっすが、待ち時間に “こち亀” と “味平” を読むのが楽しみでした。 原作は牛次郎。 いかにも、料理漫画の元ネタを考えそうな次郎っすよね。 豚太郎でも、鶏三郎でもなく、牛次郎。 関西出身なんっすかね? つい最近、 「肉じゃが」 に入れる肉は牛か、豚か。 そんな調査があって、基本、関西は牛で、関東は豚。 そんな結果が出ていたんっすが、カレーに入れる肉と同じっすな。 カレーの場合、牛と豚の境界線は桑名なんっすよね。 正確に言うと、昔っからの桑名市は牛で、揖斐・長良川を挟んだ対岸の旧・長島町は豚。 関西弁と名古屋弁の境界と同じなんっすが、んーと ここ 参照。 ほぉ、大垣でもそうなんっすかぁ。 桑名の辺りの揖斐川は長良川と合流して川幅が1キロくらいあって、生半可な覚悟では渡れないので、名古屋弁の浸入が阻止されたのは分かるんっすが、大垣の辺り、しかも杭瀬川くらいなら、簡単に侵略できそうなものなんっすけどね。 ま、それはそうと、 牛次郎 。 あ、 「うしじろう」 じゃなくて 「ぎゅうじろう」 なんっすな。 で、僕の予想に反して、東京市浅草区出身。 マジっすか? 日本の漫画原作者、僧侶、小説家、作曲家、建築家。 マジっすか? 活躍の場が幅広過ぎなんっすが、僧侶なのに牛って、エエんか? いや、牛の次郎というだけで、牛を食うとは一言も言ってないんっすが、どうして牛なのかと思ったら、本名、牛込 記(うしごめ き)。 マジっすか? “き” って、一文字の名前とか、あり得るんっすか? き君とか、貴くもないのに貴君っぽいんっすが、それはそうと、「え!!おなじ値段でステーキを!?」 これホント、酷いっすよね。 何か 『よしもと新喜劇』 にありそう。 「自分で言うたんやろ!」 とか 「記憶喪失か!」 とか、辻本茂雄にツッコミを入れられそう。 この回だけ特別に原作者の牛次郎くんがアカンかったのか、あるいは、いつもこんな調子なのか。 気になるところでありますなぁ。
で、他の話も読んでみたくなったんっすが、探してみたら 電子版 がありました。 全9巻っすか。 それくらいなら、何とか完走出来そうっすな。 で、とりあえず、お試しで3巻まで買って、第1話を読んでみたんっすが、結果、激しく後悔しました。 1冊だけにしとけばよかったぁ…。 まず最初は 「スタースパゲティの巻」 なんっすが、勝手に中身を載せて、著作権がどうのと言われても嫌なので、他人様のブログの力を借りるとすると、んーと、 これ 。 ここには載っていないんっすが、2コマ目にはテニス部だか、バドミントン部だかのJCだか、JKだかが登場します。 いいっすな。 個人的に、漫画とかアニメとかには、幼女とJSとJCとJK以外の登場人物は必要ないと思うんっすが、その点、 『のんのんびより』 は、かなり理想的っすよね。 JS×2と、JC×2の4人組。 個人的には大人っぽいJS = ほたるん、子供っぽいJC = こまちゃん。 この2人が好きなんっすが、れんちょんは性格がぶっ飛びすぎていて、ちょっと…。 JS低学年なら 『ねぇ、ぴよちゃん』 のほうが、可愛いな♪ …っと。 ひみこちゃんとの絡みが、たまらんっ♪ …のっすが、何気に、桜川よし子先生もタイプだったり。 で、登場人物は幼女とJSとJCとJKだけでいいのに、 『スーパーくいしん坊』 には男子中学生が登場します。 というか、コイツが主人公だったりします。 鍋島香介。 見た目がウザいし、性格もウザい…。 「あのねぇ、オヤジ!! おれたち若者にゃ、年季だとか腕なんて、関係ねぇんだよ」 「それよりピザパイとかスパゲティーとか、もっとナウッチイのがうけるんだよ」 台詞が最大限にウザッチイ…。 でもって、スパゲティー。 パスタとか、そういうダサいのではなくて、あくまでもスパゲティーというところが、ナウッチイっすよね。 しかも、星形のスパゲティー、スタースパ。 ほぉ、そんなん、あるんっすかぁ。 スターといえば、にしきの。 そんな世間の常識を覆す画期的なスパなんっすが、試しに 「スタースパ」 でググってみたら、いちばん上に出てくるのが 『スーパーくいしん坊』 で、その下が、弊社は世界最大6スタースパ&フィットネスを経営する、うんぬん。 そりゃ、温泉のスパやがな。 長島スパーランドのスパやがな。 スパゲティーのスパ、ちゃうがな…。 で、他にはケーキのデコレーション材料だとか、 クンフーを使用する香港スタースパ4とか。 星形のスパゲティーとか、本当にあるんか!?
…と思ったら、ありました。 疑ったりして、正直、すまんかった。 僕も大人なので、一応は謝るフリだけはしておきますが、 ほれ 。 あ、でも、よく見たらスパゲティーじゃなくてパスタだし、何かちょっと違うような気が…。 謝ってしまったのは、とんだ誤りでありましたが、もしかしてスタースパって、香介くんの自作オリジナルだったりするとか? 製麺まで手がけるとは、スーパースパ職人やんけ! が、香介くんの凄いところは、それだけではありません。 ナポリタンばかりじゃ、食べ飽きる。 そんな、糞ワガママな “味覚人 (みかくじん) ” の要求に応えるべく、イタリアン、ミートソース、バジリコ、たらこ、納豆、つけ麺風。 それら、すべてのフレーバーを一度に味わえる新メニューを捻出することになるんっすが、詳しくは、ま、誰かが書いたブログを参照して貰うとして。 結論だけ言うと、 「ワンコソバ」 から着想を得た 「ワンコスパ」 なるものを考案することになるんっすが、麺を小分けにして、色んな味を楽しめるようにする…と。 なるほど、これはなかなか、グッドなアイデアっすよね。 が、 「この量で、いったい いくつの玉が食べられるかね?」 「ふたつもたべりゃ満腹だよ」 そんなふうに言われてしまって、この味覚人、糞ワガママな上に、小食過ぎぃ! 僕ならこの時点でブチ切れて、ぶん投げますな。 ぶん投げて、宙を舞わせて、味覚人飛行物体にしちゃいますな。 が、香介くんは 「ぐぬぬ…」 となりながらも、グッと堪えて、顧客の要求に応えるべく、新しいアイデアの捻出に励むことになるんっすが、こういう姿勢は立派だと思いますね。 この量では、いくつも玉を食べられない。 じゃ、量を減らせばいいじゃん。 料理の素人である僕は、そんなふうに思ってしまうんっすが、「これ以上へらせば、料理にならねえや!!」 僕にはよく分からんのっすが、料理人 (プロ) としての拘りがあるようで…。 「1個の玉のスパの本数をへらさずに、量をへらすには…」 細かく切ればマカロニになってしまうし、うーん…。 もはやこれまで。 万事休す。 そう、思われたんっすが、ここで香介くんは画期的なアイデアを思いつきます。 「スパが」 「半分にタテにさかれている!」
無理やろ! 誰もがそう思うに違いありません。 ウドンならまだしも…。 が、香介くんはそれをやってのけます。 “氷のクギ” というキラーアイテムを使って。 これはもう、理屈ではありません。 情熱は理論を超えるっ! 事実は小説よりも奇なりっ! き君 (←原作者) は、そう言いたいんだと思います。 いや、漫画じゃん。 そう、言いたくなるんっすが、そこはグッと堪えて。 スパを半分に裂くのと、量を半分にするのと、何がどう違うんや? そう、素人は思ってしまうんっすが、それはあまりにも素人考えっす。 職業人 (プロ) にしか分からない “何か” があるに違いありません。 タテに裂いてるうちに、麺が伸びちゃうんじゃ? そんな心配もあるんっすが、そんなの、余計なお世話っす。 とにかく、味覚人は素直に負けを認めたんだから、他人からとやかく言われる筋合いは、ないじゃん! いやあ、熱い勝負でありましたなぁ。 第2話でも同じようなバトルが繰り広げられるのかと思うと、今からワクワクなんっすが、ということで、 「アニマルハンバーグの巻」 。 え? アニマル (動物) を、ハンバーグに!? 普通っすな。 豆腐ハンバーグとかでない限り、牛も豚も鶏も畜肉も、アニマルっすよね。 いわしハンバーグとかも動物だし。 あの香介くんが作るんだから、原材料が動物である以上に、何かが “アニマル” であるに違いありませんが、はにゃ〜、“あにまる” って、な〜に? 「はに丸ハンバーグ」 の誤植ではないっすよね? ということで、 これ 。 おお、エエやん♪ JCがたくさん登場するところが、個人的には当たりなんっすが、給食のハンバーグがまずくて残した香介と調理主任の間で揉め事になり、うんぬん。 ああコイツ、最悪ですやん…。 食べ物にケチをつけるヤツとは絶対に友達になれないんっすが、ま、それ以前に、この顔は生理的に受け付けられないので、一目見た時点でアカンかったんっすけど。 で、調理主任と香介くんの熱いハンバーグ勝負。 この調理主任とやらのオッサンもかなりウザいキャラだったりして、どっちもどっちやな。 そんな気がしないでもないんっすが、JCちゃんがこぞって香介の野郎を応援しているのが不快っすな。 僕はオッサンのほうを応援する側に回りたいと思います。 調理主任、がんばえー! が、よくよく考えたら、一緒に応援するほうがJCちゃんとの一体感が得られるに違いないので、僕は速攻で寝返りたいと思います。 調理主任、くたばえー! で、香介くん、何の意味があるのか、1,050グラムの巨大ハンバーグを焼き上げることになるんっすが、巨大と言えば津が誇るB級グルメ、津ぎょうざ。 アレは給食のオバチャンが、餃子をたくさん作るの、
('A`)マンドクセ
いちいち焼くのも、
('A`)マンドクセ
…というので、巨大な揚げ餃子で誤魔化したのが発端らしいんっすが、巨大ハンバーグには、いったい何の意味が? 結局、最後までその謎が解き明かされることはないんっすが、香介くんが串を刺した巨大ハンバーグをぶん投げて、宙を舞わせると、ハンバーグは見事、ぴったり150グラム×7個のハンバーグに分裂っ! で、そのひとつひとつが 「これ 子豚に にてるわ」 「あら これ小鳥よ!」 「ヘェ!こりゃ亀かな」 みたいな、微妙に動物な形になっていて、なるほど、だから “アニマルハンバーグ” なのかぁ! いやあ、目から鱗が落ちました。 形・焼き方・味。 3つのポイントで採点を競うという謎ルールの為、こんな無駄に凝ったものを作っちゃったんっすな。 形の部では、香介くん、圧勝! 無論、焼き方も味も完璧だったりするんっすが、で、最後はきっちり、調理主任と和解もします。 給食のハンバーグが糞マズくて、豚の餌にしちゃったんだけど、「あの あいびきは町のレストランのような牛肉と豚だけじゃなかったんですね」 「鳥肉や魚肉ソーセージまでが ひきこまれてあるなんて…」 一緒に挽肉にされる = ひきこまれてある。 この日本語、合ってるんっすかね? さっきはハンバーグの重さを量るスケールのことを、 「あのう、すいませんが メジャーを七個用意してくれませんかあ?」 とか言ってたし、ひょっとして日本語能力が、ちょっぴり弱い? が、料理は国語の授業じゃねぇ! とにかく、調理主任が素直に負けを認めたんだから、他人からとやかく言われる筋合いは、ないじゃん! 「かぎられた給食予算のなかで うまくて栄養のある料理をつくるためには、おれたちの知らない工夫がされていたんですね」 調理主任に、素直に頭を下げて謝る香介くん。 めっちゃ大人じゃん!
で、続いては、 「チャンコ勝負の巻」 。 あ、今度は相撲取りに喧嘩を売るつもり? 身の程知らずにも程があるんっすが、ぶん投げられて、宙を舞う羽目になるのは必須。 ま、勝手にやって下さい。 僕は心底、どうでもよくなって来ました。 が、一言だけ言わせて下さい。 「岡山名物 もみじまんじゅうはこちらですよーーーっ!!」 この台詞はアカンやろ…。 広島市民に喧嘩売っとるんか? ハァ! 牛次郎くん (←原作者) 、浅草出身で中国地方に詳しくないなら、無理に知ったかしなけりゃいいのに…。 とまあそんなことで、今回は他人様のブログに頼り切った、誰でも思いつくような突っ込みに依存した展開になってしまいましたが、 「え!! 次回はオリジナリティのある、もっと面白いネタを!?」 出来らあっ!!
ということで、今日はリー・モーガンっす。 恐らく、日本でいちばん人気の高いトランペッターなのではなかろうかと。 マイルスじゃね? そう、思われる人もいるかも知れませんが、マイルスが好きだと公言するのは、自分が初心者だと言ってるみたいで、マニアとしてのプライドが許さねぇ。 そういう人は一定数、いると思うんっすよね。 「結局、1周回って、マイルスかな (笑) 」 みたいな言い方はアリだと思うんっすけどね。 「リー・モーガンが好きっ♪」 というのも、ちょっとありきたりな気はするんっすが、変に通ぶって、ワケのわからん名前を出すというのも。 そんな思惑もあって、結局のところ、無難なところに落ち着く…と。 この人の人気の秘訣は、演奏の中身もさることながら、あまりにもドラマチックな生き様にあるのは確かなんっすが、えーと、 Wikipedia 参照。 1956年にディジー・ガレスピー楽団在籍し、その年には早くもブルーノートから 『Lee Morgan indeed!』 でデビューし、その艶やかで伸びのある輝かしい演奏スタイルから天才トランペッター・クリフォード・ブラウンの再来とも呼ばれた。 リー/モーガン、マジかよ? そういったニュアンスっすよね、初リーダー作のタイトル。 『信じられないジミー・スミス』 とか、こういうのが好きっすよね、ブルーノート。 1960年頃はアート・ブレイキー&ザ・ジャズメッセンジャーズにも所属し、トランペット奏者として、また一部の曲の作曲を手がけた。この時代の演奏では 「モーニン」 などが知られている。 これで一躍、日本でも人気者になりましたよね。 もう、アーノルド坊やと人気を2分するくらい。 リー・モーガンの曲で特に有名なのは、1963年12月21日にレコーディングされてBlue Noteレーベルからリリースされた 『ザ・サイドワインダー』 で、うんぬん。 これで本国アメリカでも不動の地位を築くことが出来たんっすが、ただ日本人からすると、ちょっと、うーん…。 ジャズ・ロック系は、めって不人気っすからね。 前回 のドナルド・バードのアルバムの冒頭がその系統で、心の底からガックリしてしまったんっすが、アレが吹き込まれたのが 「ザ・サイドワインダー」 の2年ほど前。 ドナルド・バードって、僕が思っているより、随分と時代の先を行ってた感じなんっすが、でもやっぱり、僕はモーガンのほうが、好きっ♪
ということで、今日は 『トム・キャット』 というアルバムを取り上げてみたいと思います。 1964年8月の録音。 ディスコグラフィーで言うと、『ザ・サイドワインダー』 と、その続編 『ザ・ランプローラー』 の中間に当たります。 ジャズ・ロック路線は、売れる! それに味を占めたアルフレッド・ライオンくん、ストレート・アヘッドな本作はオクラ入りにして、二匹目のドジョウ狙いで 『ザ・ランプローラー』 を売りに出すという戦略に出たんっすが、ぶっちゃけ、アホかと。 ま、商売人なので、売り上げ優先なのは仕方がないんっすが、ジャッキー・マクリーンとカーティス・フラーを配した3管編成で、リズム隊はマッコイ・タイナー、ボブ・クランショウ、そして御大 アート・ブレイキー。 これを没にする意味がわかりません。 ま、両方とも出して、共倒れになるのを防ぎたかったのでしょうが、違う路線でガッカリさせても、アレだし。 そんな思いもあっただろうし。 実際のところ、上田正樹の 「悲しい色やね」 。 僕はあの歌が大好きで、続編を大いに楽しみにしていたんっすが、次に出されたのが 「レゲエであの娘を寝かせたら」 という、まったく毛色の違った歌で、ガッカリしちゃった思い出が。 「飛んでイスタンブール」 の続編は 「モンテカルロで乾杯」 で、エエんや! 今から思えば 「レゲエで〜」 も普通にいい歌だったりするんっすが、とまあそんなことで、演奏を聞いてみることにしましょうかぁ。
出だしから3曲、モーガンのオリジナルが続くんっすが、まずはアルバム・タイトル曲の 「トム・キャット」 。 続編は当然 「ジェリー・マウス」 になるものと思われるんっすが、実際、そんなフルネームだったりしますよね、トムとジェリーのネズミのほう。 僕は子供の頃、断然 “ジェリー派” だったんっすが、大人になって即行で寝返りました。 よって、 「トム・キャット」 には期待したいところなんっすが、ちょっぴりミステリアスなムードのマッコイのピアノによるイントロに続いて、3管のハモリで、ゆったりとしたテンポで、ファンキーなテーマが演奏されます。 猫が悠然と歩いている感じっすかね? いつも走り回っているトムくんとはちょっとイメージが違うんっすが、これはこれで、悪くないな…と。 で、ソロ先発はりー・モーガン。 最初のうちは何と言うか、余裕のよっちゃんイカ。 ネズミを捕まえた猫が、なぶりものにしている感じなんっすが、やがてギアが1段、2段と上がっていって、なんともブリリアントな世界が展開されることになります。 変幻自在なブレイキーのドラミングもさすがなんっすが、で、ソロ2番手はマクリーン。 64年というと、『ワン・ステップ・ビヨンド』 の辺りっすか。 ちょっと聞くのに覚悟が必要な時期に差し掛かっているんっすが、ここではサイドマンということもあってか、リラックスしたプレイに終始していて、良好やな…と。 続くカーティス・フラーは、フラフラせずに安定しているし、で、最後はマッコイが華麗に締め。 この人、顔が恐いし、演奏はワンパターンだし、ハービー・ハンコックに比べると、日本での人気は今ひとつなんっすが、普通にピアノ、上手いっすよね。 ここではわりかし、ファンキーなフレーズをカマしてくれているし、でもって、とまあそんなこんなで、テーマに戻って、おしまい。 10分近い、わりと長めの演奏なんっすが、3管なのもあって、最後まで充実していて、エエやん♪ …と、そのように評価していいのではなかろうかと。
で、次。 「エキゾティーク」 。 ちょっぴり 「サーチ・フォー・ザ・ニューランド」 のタイトル曲を彷彿させる、そういったアレなんっすが、何か、3管ジャズ・メッセンジャーっぽいな。 そんな空気も、端々から。 ミディアム・スローの重厚なテーマは、途中からテンポが速くなって、スインギー路線に転じるんっすが、モーダルなのとエキゾチックなのが、絶妙にリミックスされているな…と。 で、ソロ先発はモーガン。 2番手はマクリーン。 どちらも、最高♪ …っすな。 ソロの後半に残りの2管が絡んでくる辺り、メッセンジャーズ色、バリバリ全開だったりして、で、以下、フラー、マッコイと、これまた、最高♪ …なソロが続いて、その後、モーガンが再登場して、一暴れして、最後はブレイキーがドラムスのソロで締めて、でもって、テーマに戻って、おしまい。 10分近い、わりと長めの演奏なんっすが、3管なのもあって、最後まで充実していて、以下同文。 テンション、高ぇぇぇ! レベルも高ぇぇぇぇ! ということで、次。 「トワイス・アラウンド」 。 タイトル通り、同じテーマのメロディを何度か繰り返す、そういったアレだったりするんっすが、リピートする度にテンポとテンションが上がっていって、でもって、ソロ先発はフラーっすか。 いいっすよね、この人のボントロ。 ネギトロみたいに味わい深いし、スカトロみたいに趣味が悪くないし。 ネギトロって言うほど、味わい深いか? 基本、醤油の味じゃね? そんな気がしないでもないんっすが、ちなみにネギトロって、葱でなければ、トロでもないって、知ってましたか? 僕は知りませんでした。 で、今、知りました。 ほれ 。 ねぎ取る → ネギトロ。 なるほど! 目から鱗が落ちた思いでありますが、このほか、ネギトロの元祖である寿司店が、よく通っていた 『むぎとろ』 と言う店の名前の語呂合わせで名付けたという説もあります。 こっちのほうは、まったく説得力がありませんな。 そんなの、ただの麦飯+とろろ芋じゃん…。 とか言ってるうちに、マクリーンのソロが始まりました。 のっけから、めっちゃテンション高いっすな。 もう、ハイテンション・タロットに匹敵するくらい。 『超・ムーの世界』 でも屈指の、どうでもいいコーナーなんっすが、そもそもサイキック芸人・キックって…。 無駄にテンションを上げればいいってもんじゃねぇ! その事を、身をもって体現してくれるんっすが、一方、マクリーンのほうは、まったく無駄ではないテンションのアゲアゲだったりして、で、その空気は続くモーガンのソロにも伝搬して、何とも熱い世界が繰り広げられることになります。 マッコイのソロを挟んで、終盤もモーガンの独壇場が繰り広げられるんっすが、最後まで緊張の糸が途切れることなく、最後はブレイキーがドコドコドコドコ。 でもって、テーマに戻って、最後は次第に速度が遅くなっていって、おしまい。 いやあ、完璧っすな。
で、次。 「トワイライト・ミスト」 。 霧に霞む都会の夕暮れを思わせるマッコイ作の名バラード。 顔は恐いのに、めっちゃロマンチックな曲を作ってくれたりするんっすよね、マッコイ。 モーガンのラッパと、残る2管との絡みが美しく、それをバックで支えるブレイキーのブラシも極上の味。 ドコドコドコドコと、無駄に叩きまくるだけのオッサンではないな。 そう、再認識させられるんっすが、で、モーガンの歌心に富んだソロは、まさしく、クリフォード・ブラウンの再来やな…と。 優等生のブラウニーと、不良代表のモーガンでは、キャラがまったく違うんっすが、意外とウマが合いそうだったりして、で、間を飾るマッコイのソロもリリカル至極で、返す返す、人間は顔ではねぇな…と。 んなことで、ラストっす。 「リゴアモーティス」 。 作曲者として M.Levy、H.Glover、J.Dell という3人の名前がクレジットされているんっすが、歌物なのか、何者なのかは、不明。 モーガンのオリジナルと言われても違和感がないようなアレなんっすが、どういう意味なのかと思って調べてみたら、rigor mortis = 死後硬直。 エエぇぇぇ…。 ま、演奏そのものはぜんぜん死後じゃなければ、硬直もしてなくて、めっちゃ生き生きとしているから別にいいんっすが、3管のハモリで、真ん中部分はピアノがリードするテーマ部に続いて、モーガン、マクリーン、フラー、マッコイの順で、各自の卓越したソロが披露されて、その後、モーガンが再登場して、場の空気を盛り上げて、最後はドラムスとの4バースで締めて、でもって、テーマに戻って、今日のところは、おしまい。
【総合評価】 この秀作をオクラ入りにしちゃったアルフレッド・ライオンは、アホか…と。 ま、いろいろと事情はあったんでしょうが、何にせよ、後年にでも日の目を見ることが出来て、よかったな♪ …と。 やっぱモーガン、最高や!