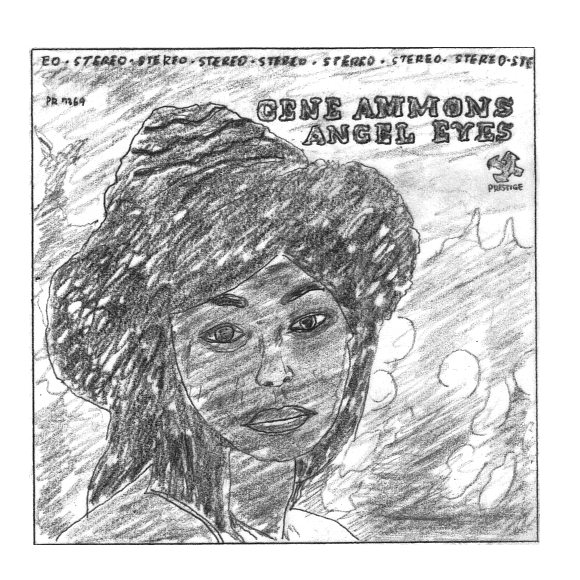 ←click!!
←click!!
衝撃の新事実。 ウスターソースは薄いから 「薄たー」 ではなかった! …ということで、調味料シリーズ第3回っす。 さすがに飽きてきたので、今回で終わりにしようかと思うんっすが、仏の顔も三度まで。 そんな諺 (ことわざ) もありますしね。 どんなに温厚な人でも、同じ事を何度もやられると、さすがにブチ切れる。 そんな様子を詠んだものだと思われるんっすが、 「仏の顔は三度まで」 ではない 。 あー。 こうやって、わざと逆張りして、マウントを取ろうとするヤツ、いますよねぇ。 人と違った発想が出来る俺、カッケェ! …みたいな。 ビタミンB1が欠乏して、末梢神経の障害と心不全による全身浮腫(むくみ)を起こしてる俺、脚気 (かっけ) ぇ! …とか、病気自慢でマウントを取ろうとするヤツもいたりするし、世の中、いろいろなんっすが、仏の顔も三度。 これ、一説には、釈迦族がコーサラ国によって滅ぼされたときのエピソードから来ているといわれています。 ほぉ、コーサラ国っすか。 あまり聞いたことがない国なんっすが、どうせなら 「甲皿国」 と漢字にしたほうが、亀の甲羅を剥がして、干して、逆さまにして、皿として使っている国という感じがして、いいと思うんっすけどね。 ま、それはそうと、コーサラ国王のヴィドゥーダバは釈迦族による無礼に憤慨し、釈迦族が住むカピラ城に3度攻め込みましたが、そのたびにお釈迦さまの説得を受けて兵を引き揚げていました。 ほぉ。 コーサラ国王のヴィドゥーダバっすか。 何かめっちゃスイング感のあるスキャットみたいな名前の国王なんっすが、シャバダバ、ドゥビドゥバ、パヤパヤ、パラッパ、ヴィドゥーダバ、ほーい♪ 最後、もうちょっとだけ、 カッコよく決めて欲しかったんっすが、釈迦族が何か、無礼なことをしでかしたんっすな。 ヴィドゥーダバ国王が憤慨するのも、もっともなんっすが、お釈迦様が 「まあまあ。」とか言って、宥めた…と。 モロ画像、法に触れると、釈尊言う。 そんな、フレッド・ジャクソンの名前を詠み込んだ俳句があるんっすが、あまり関係ありませんな。
で、まあ、ここまでの話の流れは分かるんっすが、 ところが4度目に攻め込まれたとき、お釈迦さまは宿縁を悟り、相手を説得しませんでした。その結果、コーサラ国の軍隊はカピラ城の中で残虐の限りを尽くし、釈迦族は殲滅 (せんめつ) されてしまいます。 エエぇぇぇぇ…。 お釈迦様、アカンやん! そこは説得せな、アカンやん! 傍観してたら、アカンやん! 寒かったら防寒せなアカンし、暴漢に襲われたら、傍観してたら、アカンやん! ま、誰かが暴漢に襲われている場合、下手に助けようとすると、二次被害を被ったりするので、傍観するのもやむを得なかったりするんっすが、ボーガンでもあれば、安全なところから暴漢を退治することが出来るんっすけどね。 飛び道具、最強! ま、元はと言えば、釈迦族が無礼なことをしでかしたのが争いの要因なので、殲滅されられるのも、自業自得やんけ。 お釈迦様はそのように悟ったのかも知れませんが、何か、この釈迦、アカンっすな。 この逆張り坊主は、お釈迦様は実は、4度目でも怒らなかった。 何て、心が広い! そういうことを伝えたかったみたいなんすが、いや、怒れよ! そこは怒れよ! ま、シャバダバ、ドゥビドゥバ、ヴィドゥーダバ国王の一味も、増水した川に流されて死んじゃったみたいなので、 「仏罰が下った」 ということなのかも知れませんが、釈迦族が殲滅されられる前に仏罰を下せよ! 七日後とか、何、悠長なこと言うとんねん!
ということで、ウスターソース。 …と、その前に、「酢」 について考えてみようかと思うんっすが、酢、酸っぱいっすよね。 酸っぱいの 「す」 を取って、 「酢」 という名前にしたものと思われるんっすが、じゃ、どうして、酸っぱいの 「酸」 ではなく、 「酢」 という漢字になったのかというと、さぁ、どうしてでしょうなぁ。 酢 (す、醋とも酸とも書く、英: vinegar) は、酢酸を3 - 5%程度含み酸味のある調味料。 そういうアレなんだそうっすが、そうそう、英語だとビネガーなんっすよね。 ジャズのベース弾きにリロイ・ビネガーという人がいるんっすが、あれ、 「リロイ酢」 っすよね。 …と思ったら、Leroy Vinnegar。 酢のビネガーとは綴りが違ったんっすが、言うほど酢じゃなくて、ちょっとガッカリなんっすが、いずれにろ、酢は酸っぱいっす。 が、スパイスは酸っぱくないっす。 スパイスは辛いっす。 で、スパイスと言えば、 これ 。 たまの失敗は〜、スパイスかもね♪ まいんちゃんなら可愛いから許せるんっすが、これ、もしオッサンが歌っていたら、めっちゃムカつきますよね。 失敗して、スパイスもクソもあるかい! そう、激しく糾弾したくなっちゃいます。 でも、まいんちゃんなら可愛いから、許せますよね。 「失敗す」 と 「スパイス」 を、掛けているのか! …と、深読みして、感心したりもします。 で、まいんちゃんの決め台詞、「みんなも作って、ア・ラ・モード♪」 これも、オッサンが言ってたら、めっちゃムカつきますよね。 ワケのわかんないこと、言ってんじゃねぇぇぇぇぇぇぇ! そもそも 「アラモード」 って、何や? 「あら、どうも」 なら、何となくオバチャンっぽい挨拶やな。 そんな気がして、何となく納得がいくんっすが、で、アラモードと言えば、ルックチョコ。 アラモードと書いてあるので、アーモンドの間違い? …と思って食ったら、何か、フルーツっぽいクリームが入ってるやんけ! そんな苦い経験は、子供なら誰でも一度は通る道なのではなかろうかと。 いや、苦くはないんっすけどね。 甘くて美味しくて、アラモードって、何かよく分からんけど、これはこれで、アリやな!
で、最近のルックチョコって、4種類の中に 「ナッツ」 というのがありますよね。 あれ、昔からありましたっけ? アラモードなのに、アーモンドが入ってないやんけ! そんなクレームに、いちいち対応するのが面倒になって、ひとつだけアーモンドっぽいのを入れておくかぁ。 そんな経緯で採用されたんっすかね? …と思ったら、 これ 。 え? あっ、アーモンドがメロンに変わっている! そんなこと、あったっけ? で、パッケージも箱前面からカパっと上に引き開けるようになり、以前より開けやすくなっている。 あ、これは間違いなくありました。 確かに、箱前面からカパっと上に引き開けるようになり、以前より開けやすくなりました。 で、アーモンドがメロンに変わったのは、昨年の秋からです。夏にピスタチオやヘーゼルナッツなどナッツ系のルックシリーズを出しまして (現在は販売終了)。 あ、確かにそういうシリーズ、ありましたよね。 僕は4つの味の中では 「ナッツ」 がいちばん今ひとつだったりして、何でこんなん、採用したんや? …と、不満タラタラだったんっすが、よりによって、ナッツだけ4種類とか。 誰得や? …と思ったら、 (現在は販売終了)。 不評だったんでしょうな。 当然だと思われます。 殲滅されてしかるべき黒歴史だと言わざるを得ませんが、アーモンドが、ア・ラ・モードとダブるのでは、ということでメロンに変えたんです。 そらそうや。 紛らわしいんや! アーモンドも抹殺されて当然なんっすが、最近また、復活しましたよね? 確かに 「ナッツ味」 は地味で、インパクトがないんっすが、他の3つが似たような味なので、ひとつくらいは異端児がいてもいいかぁ。 最近、そんな気がしてきたんっすよね。 歴代フレーバーの変遷を見ると、アーモンドが消えたり、復活したり、また消えたり、また蘇ったり。 葛藤の歴史が見て取れますが、ん? コーヒー? そんなヤツ、いましたっけ? 僕が子供だった昭和50年代は 「ストロベリー、バナナ、コーヒー、パイナップル」 となっているんっすが、コーヒーは、まったく記憶にありませんな。 コーヒーのチョコと言えば、 コーヒービート やろ? …と。 これ、秀逸っすよね。 味がコーヒーだし、形もコーヒー豆っぽいし。 いくら不二家が頑張っても、コイツに勝てる気がしないので、この業界からは手を引いたほうが賢明ではないかと思われますが、で、ウスターソース。 唐突っすが、本題に入ります。
コロッケにウスターソース、豚カツにも (豚カツソースではなく) ウスターソース、 海老フライや牡蠣フライにも (タルタルソースではなく) ウスターソース、家で焼いたお好み焼きにも (お好み焼きソースではなく) ウスターソース、天麩羅にもウスターソース。 え? …と思われるかも知れませんが、さば家では子供の頃から天麩羅にもウスターソースだったんだから、しょうがないじゃん! 事実は変えようがないじゃん! 「天つゆ」 とか、そんなハイカラなものは目にしたことがありませんでした。 「天つゆ」 って、ハイカラか? むしろ、ウスターソースのほうがハイカラなような? そう、思われるかも知れませんが、実際、 「天つゆ」 を目にしたことがなかったんだから、しょうがないじゃん! で、意外と美味しいんすよね、天麩羅にウスターソース。 特にサツマイモの天麩羅とか、カボチャの天麩羅とか、野菜系との相性がよかったりするんっすが、わたしは十八歳で上京するまで、天つゆというものを知らなかった。オクダ家では、天ぷらにウスターソースをかけて食べていたからである。 ほら、 奥田英朗 も言ってるじゃん! オクダ家と、さば家が日本社会のマジョリティであることは間違いないんっすが、それと同じく、餃子(ぎょうざ)もウスターソースで食べていた。 え? はぁ? さすがにそれは、ねぇわ。 オクダ家、日本社会の超マイノリティやんけ! こんな一家と一緒に餃子を食べたくありませんが、オクダ家は 「ブルーレットおくだけ」 でも置いてろって!
で、わたしの年代には、 (地域にもよるだろうが) ウスターソースで育った人間が多い。 「ソース」 と言えばすなわちウスターソースのこと。とんかつ、コロッケはもちろん、ハンバーグにも、目玉焼きにも、キャベツにもかけた。 あ、これは大いに共感が持てますな。 目玉焼きにも、もちろんウスターソース。 ハンバーグには、ケチャップとウスターソースを両方かけてた気がするんっすが、んーと、 奥田英朗 。 1959年10月23日生まれなので、僕より10コくらい上っすな。 こんなオッサンの 「わたしの年代」 と一緒にされてくありませんが、岐阜県岐阜市出身。 あ、近所っすな。 やっぱ、この辺りはウスターっすよね? 関西はウスターソースが、関東は中濃ソースが主流なんだそうっすが、ソースは こちら 。 「全国ソース人気ランキング」 というのがあるんっすが、西と東と真ん中で、くっきりと分かれるものなんっすな。 ブルドックソースというのは、名前は聞いたことがあるんっすが、実物は見たことがなくて、変な名前…。 そんな印象しかなかったりするんっすが、で、オタフクソースはお好み焼きソースとか、焼きそばソースのイメージしかなかったりするんっすが、普通のウスターソースもあるんっすかね? で、東海3県はコーミソース。 オクダ家が餃子にかけていたのも、恐らくコレだと思われるんっすが、四日市名物の豚テキ。 あれも実は、豚肉を焼いたヤツに、コーミソースをかけて食べるだけの代物だったりします。 近年はウスターソースをベースに、それなりにアレンジしたソースが使われているようっすが、で、さば家も当然、コーミソースなのかと思ったら、実はカゴメだったり。 ウスターソースは全国的にカゴメが有名で、コーミソースとか、名古屋ローカルで、けっ! …とか、馬鹿にしていたんっすが、カゴメが覇権を握っているのって、静岡と富山と福井だけだったんっすな。 福井のソースカツ丼は、カゴメソースがベース? で、イカリソースというのが、和歌山、徳島、宮崎、佐賀と、飛び地状に勢力を伸ばしていたり。 日本で初めて本格的なウスターソースを製造・販売したのがイカリソースらしいんっすが、で、いよいよ、核心に迫ります。 衝撃の新事実。 ウスターソースは薄いから 「薄たー」 ではなかった!
ドロッとして濃いのが 「とんかつソース」 、薄くて、しゃばしゃばなのが 「ウスターソース」 、その中間の濃さの 「中濃ソース」 。 ウスターソースは薄いから 「薄たー」 。 誰もがそう信じて、疑わなかったんっすが、ルネサンス期、宮廷ではソース研究がされ、17世紀には、一般家庭でも独自のソースが作られるようになった。19世紀初頭にイギリスのウスターシャー州・ウスターの主婦が、食材の余りを調味料とともに入れ保存したままにしたところ、ソースができていた。このことがウスターソースの始まりとされている。 ウスターシャー州・ウスターの主婦が発明したから、ウスターソース。 マジかよ? 秋田県秋田市上新城白山臼田(うすた)の主婦が発明していたら、臼田 (うすた) ソースになっていたかも知れないんっすな。 そういう名前だったら、「ウスターソースは薄いから、薄たー!」 そんな見当違いなことを言って、恥をかかずに済んだのに…。 臼田 (うすた) の主婦、しっかりしろ! そう、叱咤激励せずにはいられませんが、で、ウスターソース以外のソースについて触れるスペースがなくなってしまいました。 何でも 「仏の顔は何度でも」らしいので、次回は “調味料シリーズ第4弾” 、いったれー!
んなことで、今日はジーン・アモンズっす。 寺院、破門す。 そんなシンプルな一句があるんっすが、4度目は妙に諦観してヴィドゥーダバ国王の説得に当たらず、結果として一族の殲滅 (せんめつ)を招いたお釈迦様など、破門されて当然。 市中引き回しのうえ、磔獄門 (はりつけ・ごくもん) でもいいくらいなんっすが、で、ジーン・アモンズ。 好きな人は好き、嫌いな人は嫌い、どちらでもいい人は、どちらでもいい。 好き嫌いがはっきり分かれるタイプのキャラっすよね。 嫌いな人はクサくて、ダサくて、都会派アーバンな趣向にまったくそぐわないところを嫌悪し、好きな人は豪放磊落な吹きっぷりを賞賛すると。 豪放磊落と言えば、ライラック。 あの花の実から採れる汁には麻薬成分が含まれていて、乾燥させて水に溶かして発煙させて喫煙すると、ラリラリな効果が得られるらしいっすな。 が、今の法律では規制することが出来なくて、裏の世界では 「合法ライラック」 として取引されているんだとか。 今、僕が適当に思いついたデマなので、真に受けて、知ったかして吹聴すると、恥を晒すことになるので注意が必要なんっすが、アモンズのような豪放磊落なスタイルを 「テキサス・テナー」 と言うんでしたっけ? 調べてみたらアモンズはテキサスではなく、 ミズーリ州カンザスシティの出身らしいので、テキサス・テナーとは言わないのかも知れませんが、アモンズは、ヴォン・フリーマンとともに、テナー・サクソフォーンのシカゴ派の開祖のひとりである。 Wikipedia には、そのように書かれておりますな。そう言えば、シカゴ派というのもありましたか。 で、1944年にビリー・エクスタイン楽団に、1949年にはウディ・ハーマン楽団に入団しており、1950年にはソニー・スティットとデュオを組んだ。その後の活動は、麻薬の不法所持による2度の投獄によって中断されている…と。 ああ、麻薬に手を出してしまいましたかぁ。 ライラックなら合法なので、不法所持で投獄されることもなかったのに。 で、今日はそんなアモンズの 『エンジェル・アイズ』 というアルバムを取り上げてみたいと思います。 60年代のプレスティッジ盤なんっすが、有名なスタンダード曲をタイトルに持って来て、ジャケットには、むさいオッサンの顔ではなく、目力のあるギャルを採用。 アモンズ、日和ったか? そう、非難されちゃうかも知れませんが、でもまあ、クサくて、ダサいよりは、いいよね? …と。 1960年と62年、2つのセッションから構成されているんっすが、3分の2はフランク・ウェスのフルート、もしくはテナー入り。 バックは3分の2がジョニー・ハモンド・スミスのオルガンで、残りがマル・ウォルドロンのピアノ。 寄せ集め感が半端ないんっすが、実際にリリースされたのは1965年になってからだし、いろいろと訳あり風ではあるんっすけど。 目力のあるギャルを上手く書ける自信がまったくなくて、その意味では、ちょっとした “賭け” なんっすが、とりあえず演奏のほうを聞いてみましょうか。
まずは1曲目、 「ゲッティン・アラウンド」 。 デクスター・ゴードンに同名のアルバムがあるんっすが、あれには、この名前の曲は入ってなくて、こちらはアモンズのオリジナルとなっております。 「歩き回ります」 。そういった意味らしいんっすが、なるほど。 言われてみれば確かに、歩き回ってるっぽい感じの曲調でありますな。 オルガン入りのほうのセッションで、歩き回っているようなテンポで、テナーとオルガンの絡みでソウルフルなテーマが演奏されて、で、続いてフランク・ウェスのフルートのソロが登場。 この時点で、ウィントン・ケリーの 「ケリー・ブルー」 っぽい、ちょっぴりお間抜けな空気が漂うようになるんっすが、続くアモンズのソロは、さすがといった感じのドスの効いた骨太の真っ黒テナーだったりして、ブルーっぽい雰囲気は、この時点で一層されます。 で、続いてはジョニー・ハモンド・スミスのオルガン・ソロ。 これがまた 「鱧 (はも) の酢味噌和え」 ぽい味わいで、とってもジョニー・鱧の酢味噌。 オルガンを毛嫌いする人は少なくないかと思うんっすが、この人のプレイは、そんなにアーシーではなかったりするので、ぜんぜん大丈夫だと思います。 前半はシングル・トーンでシンプルに、後半はコードを交えてグルーヴィに。 で、終盤はテナーとフルートの掛け合いが聞かれるんっすが、ぶっちゃけ、オルガンとテナーの組み合わせにフルートというのは、ちょっと場違いなような? ま、そこそこ盛り上がっているような気がしないでもないので、別にいいんっすが、でもって、ソウルフルなテーマに戻って、おしまい。
で、次。 「ブルー・ルーム」 。 あまり馴染みのない曲なんっすが、ロレンツ = ハートのコンビによるスタンダードである模様。 んーと、 これ っすか。 『だるまさんのラッパ日記』 で取り上げられるくらいなので、僕が知らないだけで、わりと有名だったりするのかも知れませんが、 マイルスとか、アート・ファーマーも取り上げているんっすな。 んーと、 これ 。 おお、ホンマや。 入ってるやん。 前半のネタは読むに堪えないので無視して貰うとして、 「ブルー・ルーム」 はロジャースと ハートの曲みたいです。しみじみとしたバラードで、ベースと腐溜下痢のデュオで始まる導入部はとっても地味です。 そんなことが書かれておりますな。 腐溜下痢というのは恐らく、フリューゲルホーンのことだと思うんっすが、ファーマー版とは違って、ここでのアモンズはミディアム・テンポで料理しております。 テナーとフルートで演奏されるテーマは、ほのぼのとした牧歌系で、 ぼっかけ とか、食べたくなってきますな。 牛すじとコンニャクとか、いかにも貧乏くさい食い物なんっすが、テーマに続くアモンズのソロは、極めて快調。 古臭さはぜんぜん感じられなくて、普通にハード・バップっぽいな…と。 ちょっぴりデクスター・ゴードンっぽい感じもあったりして、いいな♪ …と。続くオルガンもソロも、悪くないな…と。 で、その後に出てくるフルートが、やっぱりちょっと場違いな気がするんっすが、でもまあ、バイ貝よりは、場違いのほうがまだマシだと思って、諦めて貰うしか。 個人的に、あまり好きではなかったりするんっすよね、貝類。 「やられたら、やり返す。バイ貝だ!」 とか言われて、 バイ貝を多量に送りつけられたりしたら、嫌で嫌で、たまらないんっすが、でもって、牧歌的なテーマに戻って、おしまい。
で、次。 「ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド」 。 ゴー・トゥと言えば、GoToトラベル、早く再開しないっすかねー。 いろいろと批判もあるようっすが、旅館やホテルに安く泊まれるというのは、おいしいっすよね。 少なくともバイ貝よりはおいしいと思うんっすが、で、えーと、歌詞は こちら 。 今年の正月に載せたのだが、アクセスが少ないようだ。見出しが悪かったせいか。 そんなことが書かれておりますが、どれどれ。 んーと、 これ っすか。 ああ、確かに。 これは酷いっすな。 ジャズに政治を絡めるな! そう、言いたいっす。 プリンにカラメルを絡めるな! …とも。 いや、それは別にいいような気もするんっすが、歌詞の中身がまったく頭に入ってこないので、他を当たりましょう。 んーと、 これ 。 『Jazzと読書の日々』 。 このブログ、わりとよくヒットするんっすが、「go to my head」 には 「酔っぱらう」 と 「混乱する」 の二つの意味があって、それを掛け言葉のように使っている歌。 だから、お酒の喩えが次々出てきます。 ほぉ、なるほど。 ぶっちゃけ、何か今ひとつ、ピンとこなかったり するんっすが、酔っぱらいの戯言 (たわごと) だと思えば、ま、こんなもんかと。 で、歌詞はともかく、曲のほうは完璧っす。 アモンズはバラードとして演奏しているんっすが、フルート抜き、ピアノ入りのシンプルなカルテット編成。 イントロなしで、ピアノ・トリオによるテーマから始まるんっすが、いいっすなぁ、この雰囲気。 たまらんっすなぁ、マル・ウォルドロン。 で、そうこうするうちに、ジーン・アモンズが登場。 ベン・ウェブスターほどではないんっすが、十分に “魅惑のムードテナー” してます。 男臭くて、不器用で、器用貧乏で、貧乏暇無しで、いや、どんどん言いたいことからかけ離れてしまいましたが、とまあそんなこんなで、テーマに戻って、おしまい。 いやあ、やっぱ、バラードはオルガンよりもピアノっすなぁ。
…とか思っていたら、次。 アルバム・タイトル曲の 「エンジェル・アイズ」 。 今度はオルガンをバックにしたバラードだったりするんっすが、これはこれで、悪くないな…と。 で、歌詞は これ 。 超有名な曲のわりに意外と歌詞が難解で、みんな翻訳に苦労している模様。 そういうアレなんだそうっすが、確かに訳詞を読んでみても、あまりピンと来ませんな。 おめめが天使みたいで、可愛いな♪ そんな、たわいもない歌詞なのかと思ったら、違うんっすな。 そうと分かると、アモンズの吹きっぷりも、何だか苦悩に満ちているように聞こえてきたりするんっすが、オルガンの短いイントロに続いて、テナーでテーマが演奏されて、そのままソロへと入っていく。 そういう流れでありますな。 で、続いてフルートのソロが登場。 今までは場違い感が否めなかったんっすが、ここではすっかり溶け込んでおりますな。 で、続くオルガンのソロも、なかなかいい感じだったりして、でもって、テーマに戻って、おしまい。 ということで、買ってきましたぜ、ルックチョコ。 今はバナナ、アーモンド、ストロベリー、パイナップルという面子なんっすな。 アーモンドも、これはこれで、悪くはないな。 そんな気がしないでもなくて、でもやっぱり、フルーツ味のほうが、美味しいな♪ …と。
ということで、次。 フランク・ウェスのオリジナルで、 「ウォーター・ジャグ」 。 ジーン・アモンズは、アメリカ合衆国のジャズ・サクソフォーン奏者。 (中略) 「テナー・サクソフォーン界のボス(The Boss)」 や 「ジャグ(Jug)」 の愛称でも知られる。 それにちなんで曲名を付けたんでしょうが、Water Jug = 水差しっすよね。 ここまでの快演に水を差されるんじゃないか? それが、ちょっと心配だったんっすが、ぜんぜん大丈夫でした。 むしろ、ここで一段、加速する感じ。 無論、作曲者も演奏に参加しているんっすが、ここではフルートではなく、テナーサックスを吹いていて、結果、それがいい方向に作用した模様。 テナー2本のバトルは、定番っすからね。 曲そのものは典型的な “ゴスペル” で、都会派アーバンな僕の趣向に合致するものではないんっすが、この編成なら、ぜんぜんアリやな…と。 2管のユニゾンでテーマが演奏された後、まず最初にテナー 「1」 のソロがフィーチャーされるんっすが、これは恐らく、ジーン・アモンズではなかろうかと。 フレージングを詳細に分析した結果、そのような回答が得られたわけではなく、普通、リーダーに敬意を表して、先にソロを吹いて貰うやろ? そんな社会生活上の通念によるものなんっすが、で、続いてフランク・ウェスとおぼしき人のソロが登場。 テナーを吹かせれば、それなりに豪快だったりするんっすが、その後、再びテナー「1」が出て来て、「2」が続いて、また「1」に戻って、「2」が出て来て。 それを何度も繰り返すことになるんっすが、その交代の間隔がだんだん短くなって、次第に熱くなっていくというのが、お約束。 で、その後、オルガンのソロが出て来て、でもって、テーマに戻って、おしまい。 全体としては、わりと短めで、もうちょっとバトルを堪能したかったような気もするんっすが、ちょっと物足りないくらいが適正だったりするのかも?
んなことで、ラストっす。 ピアノ入りカルテットのほうのセッションで、 「イッツ・ザ・トーク・オブ・ザ・タウン」 。 「街の噂」 という、いい感じの邦題があったりするんっすが、 ググってみたら、レスター・ヤングのバージョンがありました。 ほれ 。 おお、いいじゃん♪ で、 ついでにコールマン・ホーキンスのバージョンも。 ほれ 。 おお、これもいいじゃん♪ 2人のテナーの巨匠のトーンの違いが明確で、何とも興味深い聞き比べでありましたが、で、アモンズはどうかというと、音色的にはホーキンスっすよね。 ホーキンスのトーンで、レスター・ヤングのフレーズを吹くというのが、モダン派テナーの原型なんだそうっすが、アモンズのこれは、それのひとつの完成形と言っていいのではなかろうかと。 ピアノのイントロに続いて、アモンズが切々とテーマを歌い上げ、とっても切ない気持ちになったりします。 もう、100均で買ったハサミと同じくらい、切ない気持ちになるんっすが、あまりにも切れなくて、切ないっすよね、あれ。 でもって、そのままテナーのソロに入って、でもって、テーマに戻って、おしまい。 ということで、今日は以上っす。
【総合評価】 あまり多くは期待していなかったんっすが、普通によかったっす。 全然よかったっす。 強いて言えば、フルートがちょっぴり場違いだったのと、バラードが2曲、それ以外が4曲という構成のほうがよかったかな? そんな気がしないでもないところが、ちょっとアレだったんっすが、アモンズは普通にハード・バッパーだったし、オルガンも悪くはなかったし、ピアノ入りの曲があるのも変化があっていいし、ジャケットのお姉さんは目力があるしで、アモンズを何となく毛嫌いしていた人でも、普通に楽しめる気がして、オススメ☆